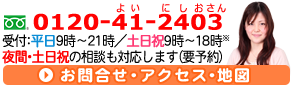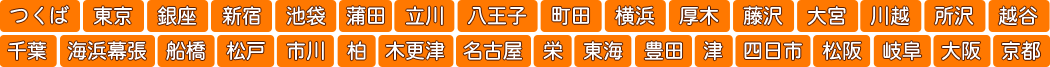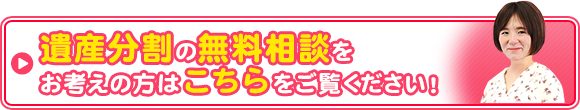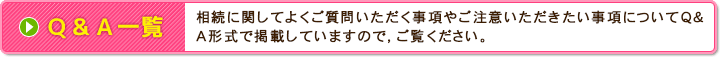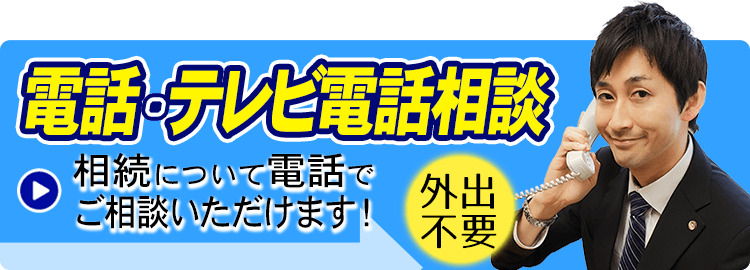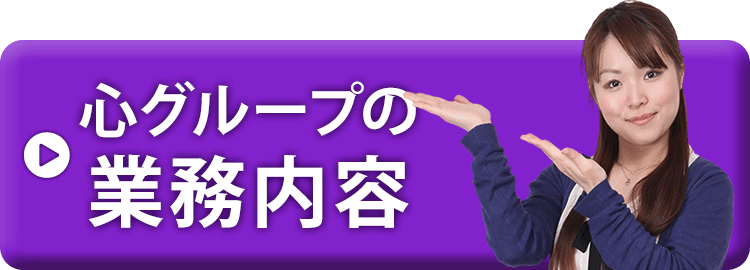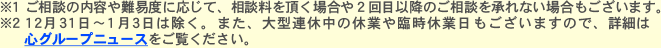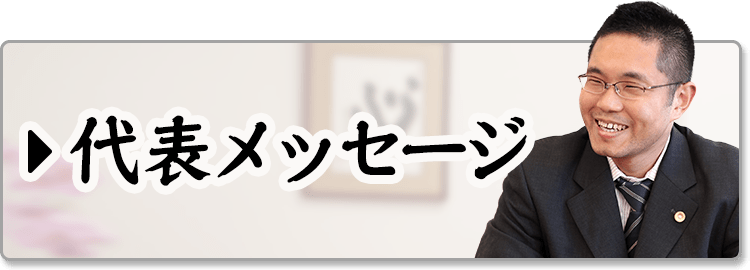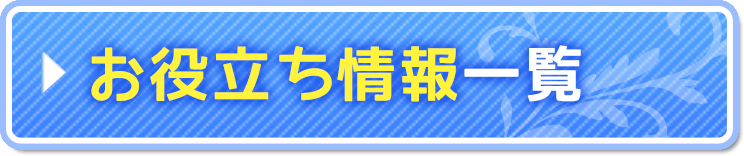遺産分割協議で相続人が全員そろわない場合の対処法
1 相続人の特定・所在調査
遺産分割協議を行う前提として、相続人がそもそも誰か分からない場合や、相続人が誰であるかは分かっていても居場所が分からない場合があります。
相続人が欠けていると、有効な遺産分割協議を行うことができないため、まずは戸籍や住民票調査を行い、相続人を特定し、居場所を確認する必要があります。
相続人が分かっていたとしても、手続きを行うためには戸籍が必要となるため、いずれにしても資料の収集は必要です。
2 相続人が所在不明・生死不明の場合
住民票の調査を行った結果、住民票が消除されている、住民票記載の住所にはその相続人以外の第三者が住んでいて住民票と実態が異なる、周りの者も誰も行方を知らないといった事情により、相続人の現住所が分からない場合があります。
その場合、その相続人に財産管理人がいない場合には、不在者に代わって遺産分割協議を行うため、不在者の財産管理人を選任するよう、家庭裁判所に申し立てることができます。
不在者が一定期間生死不明の場合、失踪宣告を申し立てる方法もあります。
失踪宣告により、その相続人は法律上死亡したものとみなす効果を生じさせることとなります。
3 相続人が話し合いに応じない場合
相続人の特定や所在については問題がなくとも、連絡をしても話し合いに応じてもらえない場合もあります。
そもそも、その相続人が相続に関わりたくないという意向であれば、その相続人自身が相続放棄の手続きを行ったり、他の相続人に対して相続分を譲渡したりすることで、関わらなくて済むこととなります。
しかし、そういった手続きをとることもなく、連絡をしても反応が得られないような場合は、もはや裁判外での話し合いは困難であると思われます。
その場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停委員・裁判所の関与のもとで話し合いを行うことができます。
調停においても、相続人が必ず出頭するとは限りませんが、裁判所からの連絡があることによって応じてもらえることも多いと思われます。
調停でも解決しない場合には、最終的には審判で解決を図ることとなります。